【障害年金の受給に必要な3要件】
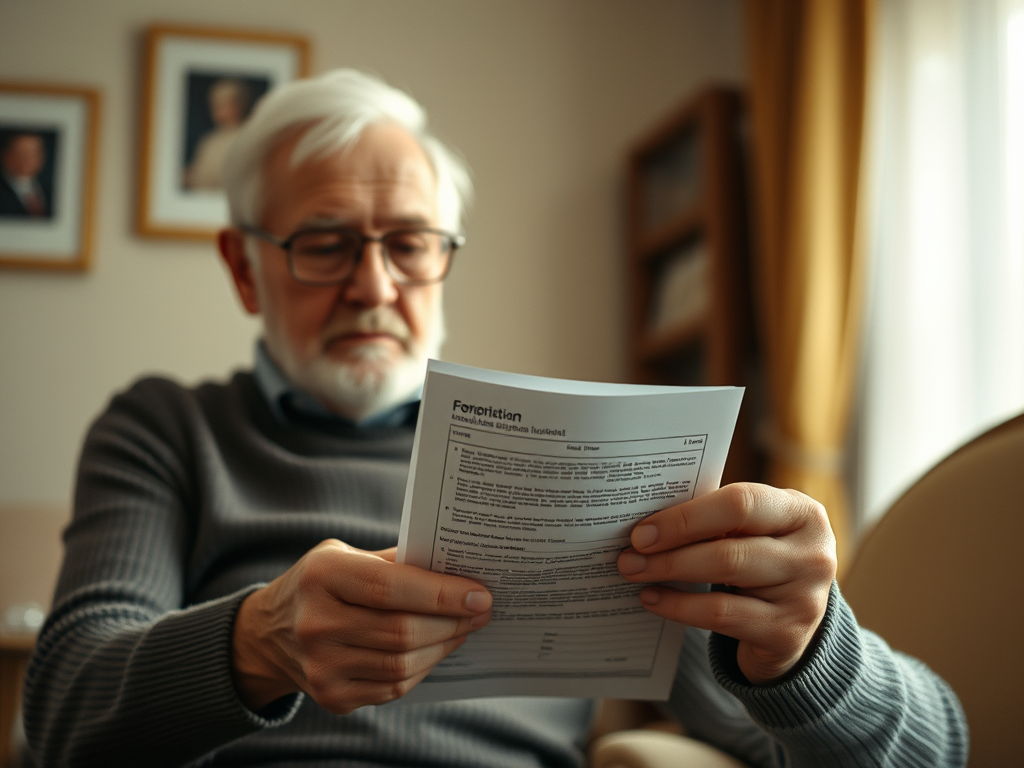
加入要件
・障害年金を受け取るには『初診日』が年金の加入期間中でなくてはいけません
・つまり国民年金か厚生年金の被保険者中に『初診日』がある事が必要です。
・例外として、『初診日』が60才以上65才未の期間にあり日本国内に住んでいる人、20才未満の期間にある人も加入要件を満たします。
保険料納付要件
・保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において初診日の前々日までの全被保険者期間の3分の2以上の保険料納付期間があるか、又は初診日の前日のおいて初診日の前々月までの直前1年間に滞納期間がない事が必要です。
・つまり初診日の前日において所定の保険料を納めていないと、受給出来ないのです。上記の保険料を初診日以降に納めても、要件は遡って満たせません。
障害要件
・障害要件とは『障害認定日』に規定の障害の状態にある事です。
・『障害認定日』とは初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月経過する前に傷病が治った日(症状が固定した日)です。
・『障害認定日』には「人工透析の実施から3か月を経過した日」など11項目の特例があります。
・既定の障害の状態は、国民年金法や厚生年金法に規定があり、日本年金機構のホームページの「障害認定基準」に詳しく具体的に記載されています。
障害状態は障害等級表の1級、2級、3級(厚生年金のみ)、障害手当金(厚生年金のみ)に該当する状態です。
〚申請方法〛
障害年金の申請(請求)は年金事務所や医療機関などへ出向き相談や診断書などの作成依頼が必要です。

年金事務所等への相談
・最初にすることは年金事務所(国民年金は市町村役場年金係でも可)に出向き、相談をする事です(年金事務所は予約が必要です)。
・初診日から現在までの障害年金の対象となる傷病の受診歴と症状の推移をまとめておくと良いでしょう。
・基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)と本人確認書類(代理人は委任状も)を持参する。
初診日と納付要件の確定(年金事務所等にて)
・受診歴を話し初診日を確定してもらい、保険料納付要件を調べてもらいます。
・保険料納付要件が良ければ、請求に必要な書類一式を渡してもらえます。
・その後の手続きを説明してもらい、当日の相談は終了です。
受診状況等証明書(初診証明)の取得
・初診日の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼する。
(現在の医療機関が初診日も同じなら不要です)
・初診日の医療機関が廃院、終診より5年以上経過してカルテがない等で受診状況等証明書が取得できない時は、受診状況等証明書が提出できない申立書と参考資料が必要です。
・生来の知的障害は受診状況等証明書は不要です。
診断書の取得
・障害認定日から3か月以内の診断書を取得する。
(障害認定日に障害等級に該当していない場合は不要)
・20才未満傷病で20才到達時が障害認定日の場合は20才到達日前後3か月以内の診断書が必要です。
・認定日から1年以上経過している場合は、事後重症請求の診断書を取得する。
(診断書の現症日は年金請求日以前3か月以内のもの)
病歴就労状況等申立書の作成
・自分で病歴就労状況等申立書を作成する。
・知的障害など傷病が生来の場合は出生時から記載する。
年金請求書を年金事務所等に提出
・受診状況等証明書・診断書・病歴就労状況等申立書など必要書類を提出する。
結果通知が届くのを待つ
・請求日から3か月程度で自宅に郵送されます。

